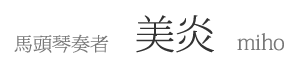2016
こころがなく- 2016/03/14 -
なんであんなに心が泣いたのか。なけてしょうがないひと時でもあり、楽しくてしょうがないひと時でもあった昨日。
戦国時代里見一族の小説の挿絵を描いた、山鹿公珠さんの作品展示会と、小説の作者の夢酔藤山さんの講演会にて馬頭琴を演奏しました。
今回はキーボード竹井美子さんと、パーカッション前田仁さん。
山鹿先生のところへは、ライブの他にもちょくちょく遊びに行くのですが、その度にシルクに描いた墨絵の布をいただくので、今回はMEKANSEI さんの協力のもと、その墨絵の布を衣装にして、ライブに間に合うように仕立ててもらいました。
その衣装がこちらです。


山鹿先生は本当に小柄でとてもチャーミングで柔らかい可愛らしい方なのに、筆持つとかわる。笑
山鹿先生ファンが東京からもたくさんこの千葉の房総の山奥に来ます。
昨日は男性も女性も着物を着た方がいらしていて、なかなか独特な雰囲気でした。
戦国時代の里見一族。
里見の子孫の方がおこした、里見流の日本舞踊の方々が楽しい方達で、話に花が咲きました。
男舞や剣舞や様々な踊りが見れました。
休憩をはさんでその後演奏がはじまると、100枚の山鹿先生が描いた戦国の絵が語りかけてくるようで、そして、里見流の方々が舞った後の空間が、なんだかとにかく、ここは里見の城の中で、ここにいる人たちまでが、その時の人達のような錯覚を覚える程でした。
というか、このギャラリー、すぐ山の上が、滝田城の跡です。
ギャラリーに来る前にいつも間違えたことないのに、今日はなんの違和感もなく城跡の方の山道に車で入ってしまい、慌てて引き返しました。笑
一つわかったことは、私のオリジナル曲、最後の鷹、この曲の一つのエピソードとして、ネイティヴアメリカンの人が、着飾って戦いに出るのは、士気を高めるためではなく、戦いで死んだ時に、神様の前に行く時のためだという話が、とても心に残り、曲を書きました。
戦わなければいけない運命というのが、あるような気がしたのです。
この挿絵だけを見ていても、どんな戦国の世だったのか、この時代にうまれ、その家に生まれたことが何を意味し、どんな運命を歩んだか、手に取るようにわかります。
山鹿先生、実際に見てきたんじゃないの?と皆さんが言うくらい、一つ一つの絵と、出来事が胸に迫ってきて、私は泣けるのです。
その絵に囲まれて、この曲を弾く時に、
誰も人を殺したくはないし、殺されたくはない。
でもそのような世に生まれ、そうせざるを得ない時、そのような運命があるのだと、思わずにはいられません。
と、一体私は何に向かって、誰に語りかけているのか、とふと思いました。
そして演奏した時に、心が泣くとは、こういうことか、と思いました。
実際に私は泣いてはいません。
自分が悲しいのか、何が悲しいのか、とにかく、悲しくて悲しくて悲しかったです。
もちろん、風の馬という元気なオリジナル曲などで、また気分も感じもかわりますが、やはり、最後に今日の日にちょうどいいなと思った、オリジナルの月みちるを演奏しました。
実はこの曲も、最初はお月様を見て、浮かんだメロディーなので月の曲だと単純に思っていましたが、弾くたびに、荒城の月のイメージが湧いてきて、とうとう今日は、荒城の月からの月みちるを演奏しました。
山鹿先生が、今日は、ほとんど泣きっぱなしだったわ。
絵の人達が喜んでいたわね。と言いました。
悲しくて泣くことで癒されることもあるのだなと思いました。
そして、それが喜びになる。
美炎さーん。美炎さんの為に描いちゃった。
着てね。
とにっこりしてくれた馬の!馬のシャツです。表にもいます。
そんな場所とご縁が少しずつ増えてきて、本当にありがたいなと思います。
最後に皆さんで撮った写真。
山鹿先生の旦那さんが撮ってくれました。
載せたいところですが、山鹿先生のところは、ネットやデジタルではないので、残念。
てなわけで、その旦那さんのおさむさん。
宮大工ができるような腕前の面白い人です。
6月にはまた書き上げる、更に100枚の絵と、琵琶とソプラノと踊りのコンサートがあるそうです。
そして、まだ未定ですが、11月には、最後の100枚の展示の時に、また馬頭琴で色を添えられるかもしれません。
どうぞその時はお越しください。
2016
飛んで- 2016/03/12 -
こうふくのしま
その詩のご縁で昨晩は新宿経王寺の慰霊祭へ。
飛び入り演奏してきました。
飛び入り演奏とはよく言ったもので、迷いながら着いたら、すぐにお願いします。ということで、ほんとに飛んで入って弾いてきました。
このように集って皆さんで思いを一つに祈る機会というのはいいものだなと思います。
そして、その機会が与えられたことに感謝でした。
作家の田口ランディさん。めちゃくちゃチャーミングな方でした。
そして、お寺の住職がとても気さくな方で、個人的には、若い頃畜産科でアメリカに牧場実習に行っているところが、なにか親近感を、覚えました。
私も高校時代は畜産部で牛の世話をして、といっても、トラックで出かける山の草刈りが好きすぎて、ほとんどじゃんけんに勝つと、ヨーロッパの死神が持っているような身長より長い鎌を担いで、ひたすら草刈りをして、帰りに山になったトラックの後ろの草の中に埋もれて帰るのがやみつきでした。
音楽でみなさんと心を共にする、音楽で思いをはせる。
やはりいいひと時だなと思います。
打ち上げの時に、なぜかランディさんに一口占いしてもらったのが、印象強いです。笑
何を言われたかは内緒^ ^
いろいろな方とお話できて良かったです^ ^
2016
タナダダ- 2016/03/12 -
六本木。
茂さんの棚田。
そこからできた梅平の人達の輪。
それを作った仕掛け人、ヒロクラフトの廣田さん家族。
まるまる六本木にて
展示されていました。
というより、廣田さんの長女、萌さんが作った5年間の棚田コンサートの記録が素晴らしすぎて、こりゃ私の宝物です。
棚田コンサート自体が私にはご褒美であり、初心にかえれる場所であり、人の輪や暖かさ、ふるさとを感じられる場所であり、棚田コンサートにかかわる一人一人がかけがえのない人達で、そんなことをあらためて感じられる記録になっていました。
こんな風に記録として残ると、5年前のまだいろいろ足りなかった自分をみると、この5年という月日がとても長かったような、あっという間だったような不思議な気持ちです。
このように迎えてくださる棚田での皆さんがいるから、自分なりにこたえようとしているうちに、いろいろなものが磨かれたのかもしれません。
だいたい、表現はともかく、表面が、あまりにもこだわらなさすぎて、自分でも面白い。
ショートカットだったこともあり、下手すると少年。
いえ、実際そのように間違われていましたね。化粧もしなさすぎて、今考えると舞台に立つものとして恐ろしいですが、山の中から下りてきました。という勢いで弾いてました。
それはともかく、梅平の人達の垣間見る優しさやこだわりが、実際その人の言葉でインタビューを読んでみると、より身近に感じられました。
萌さんの自由な発想と、この棚田を育む梅平で培われた自然を思う気持ちが、去年の棚田コンサートのトータルコーディネートや、梅平のおばあちゃん図鑑や、里守人のお米プロデュースや、様々なものに現れています。
これから、このデザイン力を生かして就職活動、東京を目指しているそうですが、ぜひいいご縁があるといいと思います。
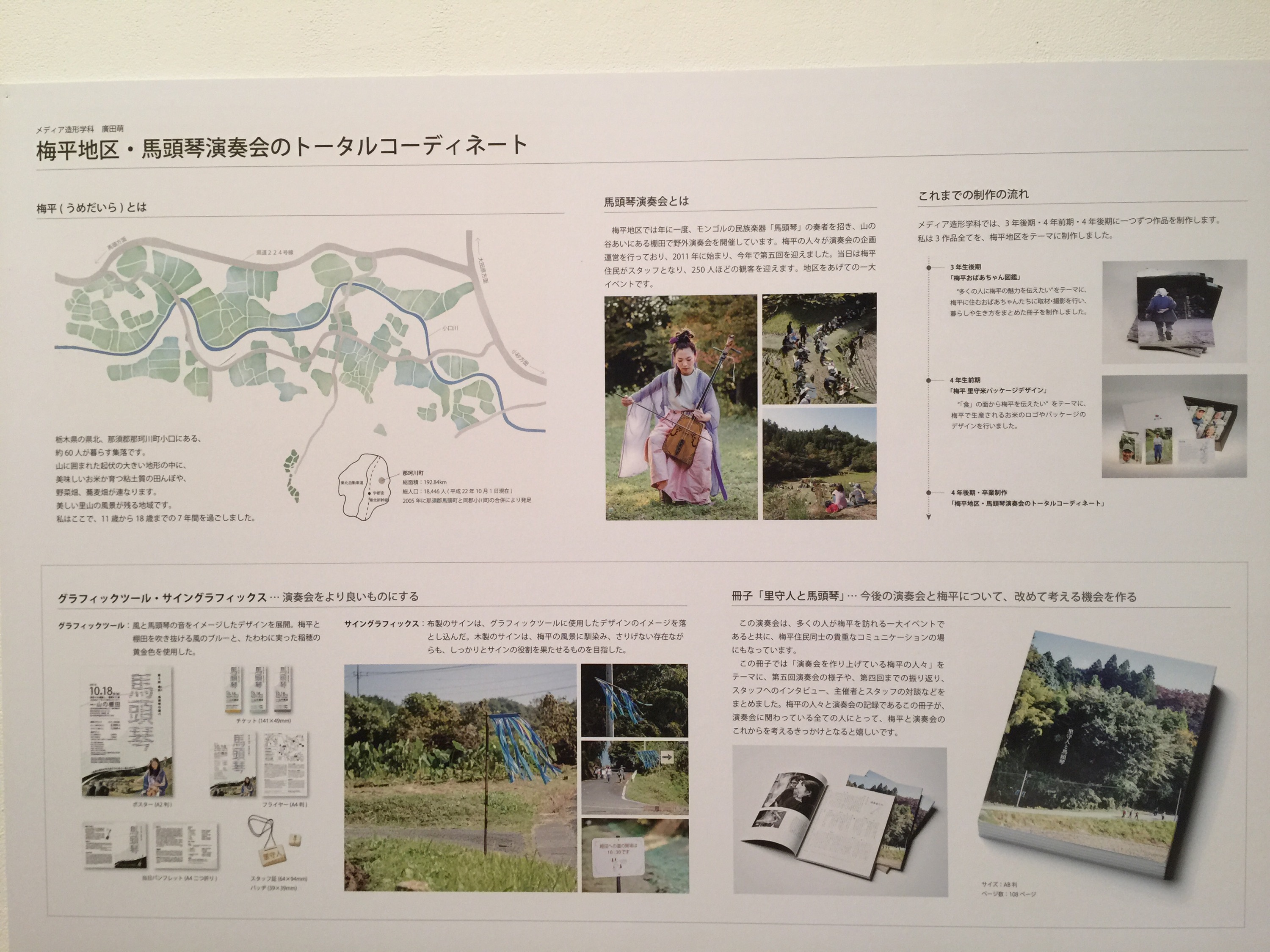

この展示会にいらしたお客様のノートに、棚田コンサート行きたいです。
という感想が多く、萌ちゃんのこれもコーディネート力だなと思います。
冊子の中に登場する、里守人おじさんずのコメントも面白いし、ぐっときますが、私一番の嬉しいコメントは、何気に廣田さん次男のメイ君の、馬頭琴の音楽好き。
というコメント!
単純に嬉しい!
ますます、今年、どんなお返しができるか、これからまたより自分を磨いて、棚田へ行きたいと思います。
2016
この日に想うこと- 2016/03/11 -
2016
心の中の火種- 2016/03/04 -
言えないことってたくさんあるんだなーと最近よく思う。
言いたいことを言うことが表現ではないんだな。
今日は二つの絵の展示を見てきましたが、まったく違うものでありながら、表現し続けることについて思わず自分のことも振り返りました。
自分の心の中にある火種のようなもの。
それがあるから続ける。
何度も見失いそうになり、何度も道をそれるのだけれど、たちかえれるのは、その火種があるから。
例えば人を喜ばしたい。とか、いろんな事が言えるし、いろんな要素を体験もするけれど、それはやはり結果であって、いいことでも悪いことでも、単に結果であって、
本当にやる理由というのは心の中の火種なんだな。
そのことを突きつけられて、良かった。
火種を自分で消さないように、どう維持し、時に炎を立ち上がらせ、時に消えない程度に鎮める。
そうやって自分の中にある火種と一生付き合うこと。
もう運命なのだと思う。それは。
今日のことは忘れない。
人はみんな違う。
私の中の火種を私の炎に。