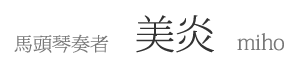2014
- 2014/08/06 -
山形へ
高校時代を過ごした場所
飯豊山の懐
温泉に浸かって飯豊連峰を眺める
自由なものは
自由な精神から生まれる
自由な精神を育むものは芸術
芸術の源は自然
自然とは私
私の本質は自由な精神
夏に来るのは久しぶり
圧倒的な緑
こんこんと湧き出るような緑
見てると自分が溶けていきそうだ
自然が好きとか嫌いとかいうけれど
私の感覚では
外にある対象をこえた
自分を含む
もっと大きななにか
今だって私はここに溶け込むように存在している
その感覚がなければどう生きたらいいか分からなくなる
不自由なものを自由だと思い込む
自然と同調することを忘れた感覚を調律するように
繋ぐものが芸術の役割
メロディー
ハーモニー
リズム
演奏している時にうまれるその瞬間の間や
自由なテンポや
音のうねり
あれはぜんぶ
風であり
波であり
あらゆる森羅万象
それはぜんぶ
吐息であり
涙であり
笑い声
あらゆる感情
ここで山や川で遊んで得た感覚がテンポや間や空気にとってかわる
今までの悲しみや喜びすべての感情は
音にかえることができる
どう生きるかなんて考えてみても
マンダラのように
すべては渾然一体
それを眺める視点を持てたら
それは人として可能なのだろうか?
突然インスピレーションによって
一瞬だけ与えられるギフトなのだろうか?
あまりにも緑がすごいので
いろんな事を思い出した
そういえば自然の中で暮らすことは小学生の頃からの夢だったなー
2014
どこに所属する?- 2014/08/02 -
今朝はみなとみらいへ
去年、一昨年と馬頭琴で参加したハマのJack主催の絵本コンサート。
今年は客席からゆっくり鑑賞。
馬頭琴では「スーホの白い馬」でしたが、今回は「おおきななぶ」「にじいろのさかな」でした。
いろいろな趣向を凝らしていてとても楽しめました。
作曲の木村裕くんの紹介でクラシック界で活躍されている方々と、何度か共演する機会を与えられて
今回客席で聞いてよりはっきりと
とろけるようなアンサンブル。
そして音の響き方や、色が同じ輪を描いている。
馬頭琴はおそらく全然違う色で、輪というよりもその輪を突き抜けるようにして、音が出ていたかと思うと、
これはやはりメインで暴れるより他にない楽器です。
を、再確認。
というよりも、あきらめ。
クラシックの曲も、だったら違って弾けてしまって仕方ないのです。
モンゴル民謡にもまた、けっして精通していないわたくし。
主に内モンゴルの神的存在であるチ・ボラグの作曲したものと、彼編曲の民謡、演奏スタイルもまた、それ譲りです。
ボラグさんの曲はモンゴルの何もかもを、文化として体現しているものなので
内モンゴルの他の曲が、その真似に聞こえてしまうのは仕方ありません。
私が自分で曲を作るようになって
ボラグさんは言いました。
「美炎の作る曲は、私と共通しているものがある。
それは日記と同じです。」
言われた時はよくわからなかった。
なんとなく今
おぼろげにわかる気がします。
とにかく、この馬頭琴という楽器でもって
クラシックでも民謡でもJAZZでもなんでもない
音楽をしていくしか、ないんだなーと。
明日もまた、みなとみらいでハマのJackさんコンサート
ドボルザークのアメリカ
レナード・バースタインのウエストサイドストーリー
聞いてこようかな。
ドボルザーク大好きです。
チラシにクラシック界随一のメロディーメーカーとかいてあって、本当に。
と思って嬉しくなります。
メロディーって何だろう?たまに考えます。
でも私にとっては、メロディーと音色という要素はいつまでも大切にしたい。
いつでも、どんな時でも。
でも、所属するところがどこにもないわたくしです。
いいか。
いいね。
ところで、帰ったら花火大会でした。
たまたま見たところが、アパホテルにかぶってる芝生広場で、
後ろにいるお兄さんが
「出た!アパ越え!」
「おしい!低いぞ!アパ越えならず。」
と、スキージャンプの実況みたいなコメントを叫んでくれていたので倍楽しめました。
そしてこんな素敵な夏の水菓子にも出会えて、良い1日でした。
2014
高原- 2014/07/30 -
ただいま1130メートルに滞在中です。
ピアニスト竹井さんと、写真を撮って遊ぶ。

上向き過ぎました。

というより、このブログの更新に四苦八苦です。
よくある猫の置物ごっこ。
前回、浅間山の鬼押出しへ行った時に見た風景が、出来たばかりの作品 Five elements
に雰囲気がピッタリだったので、この作品をよりスマートに編集したいと思い、
今回は楽譜と音源も持って、竹井さんとこの景色を眺めながら、作業しよう!
という決意をここで表明。しとかないと
・・・。
というか、鬼押出しで演奏できたらいいな〜。