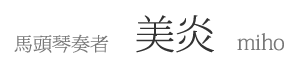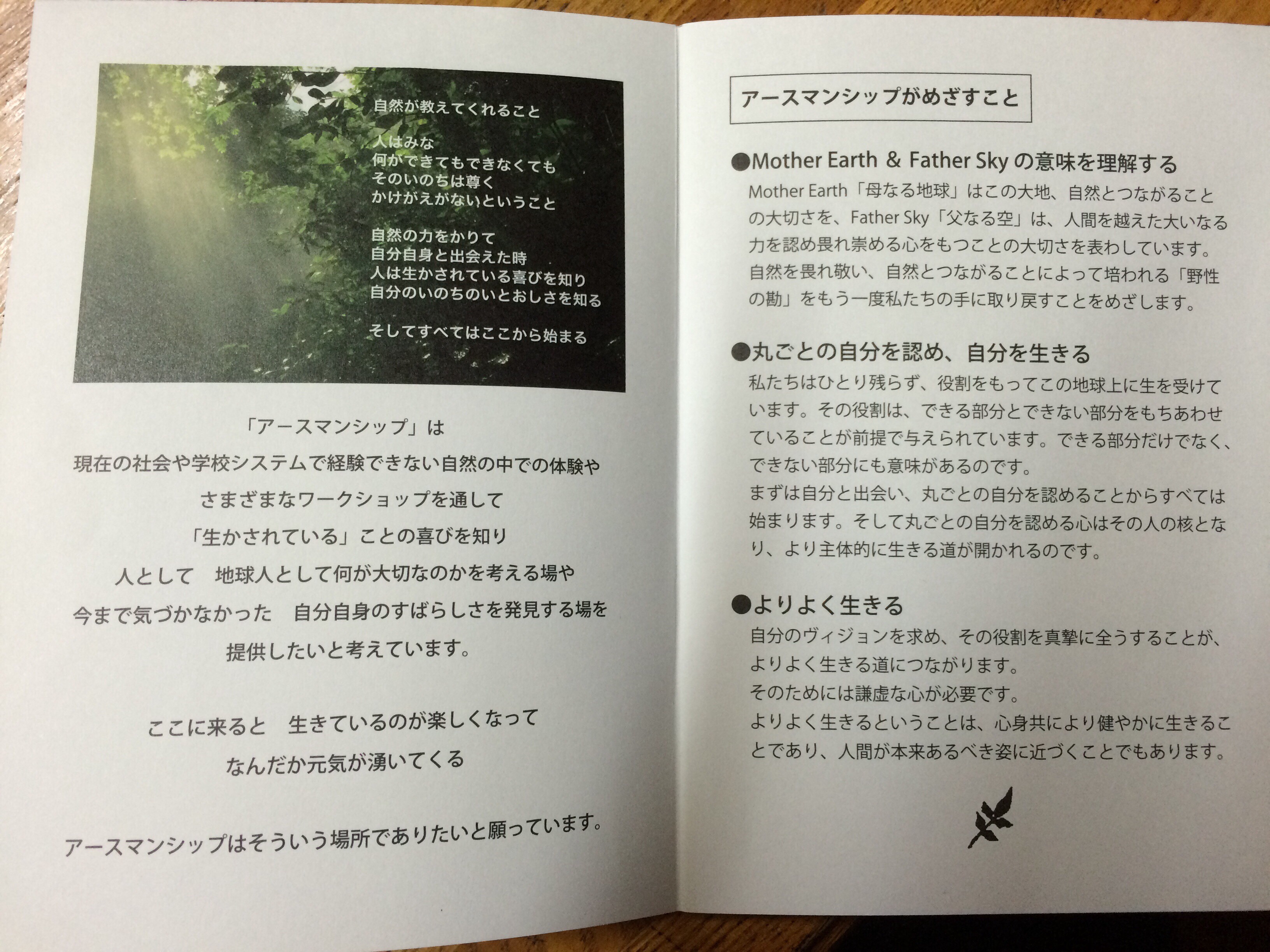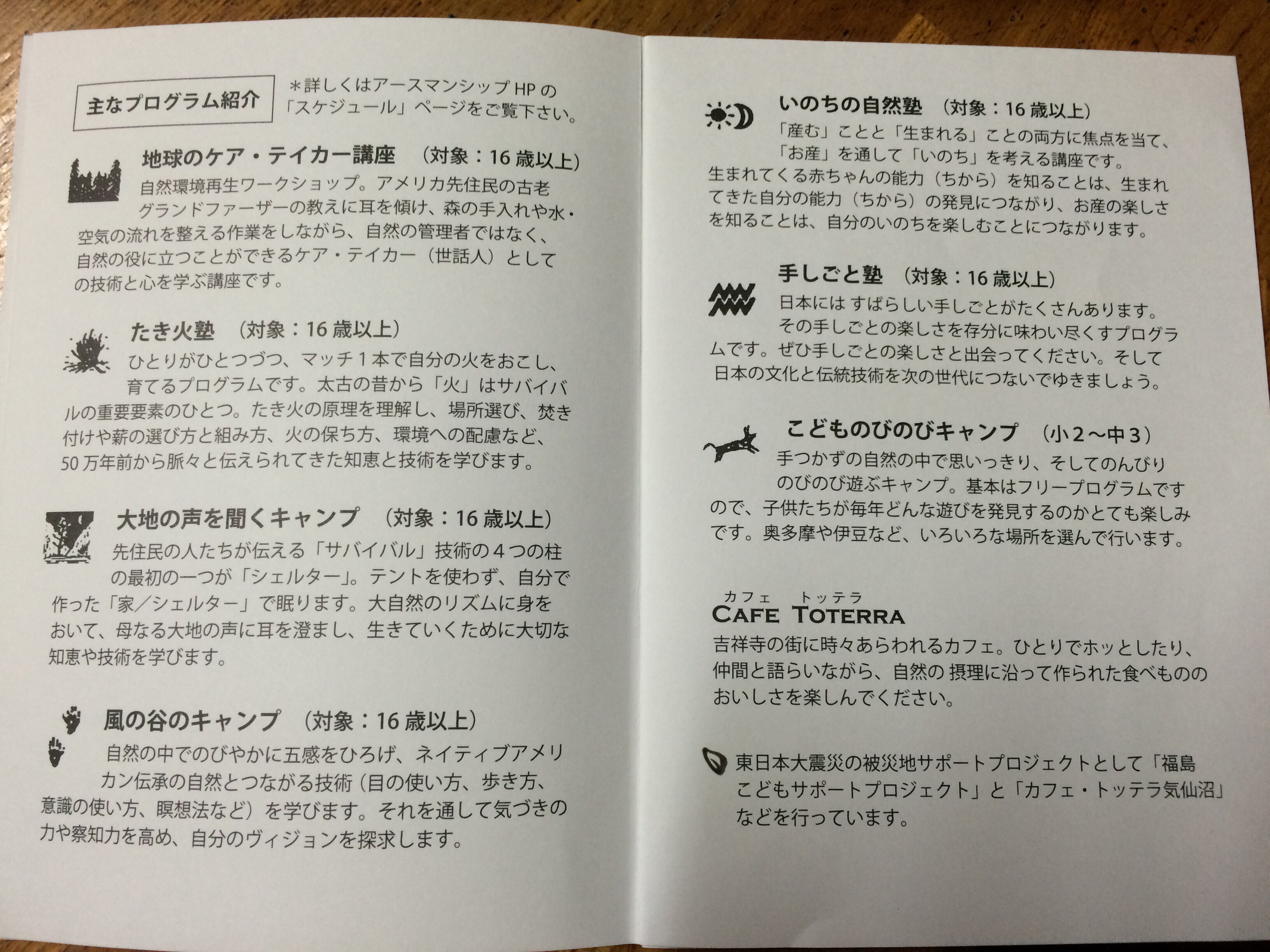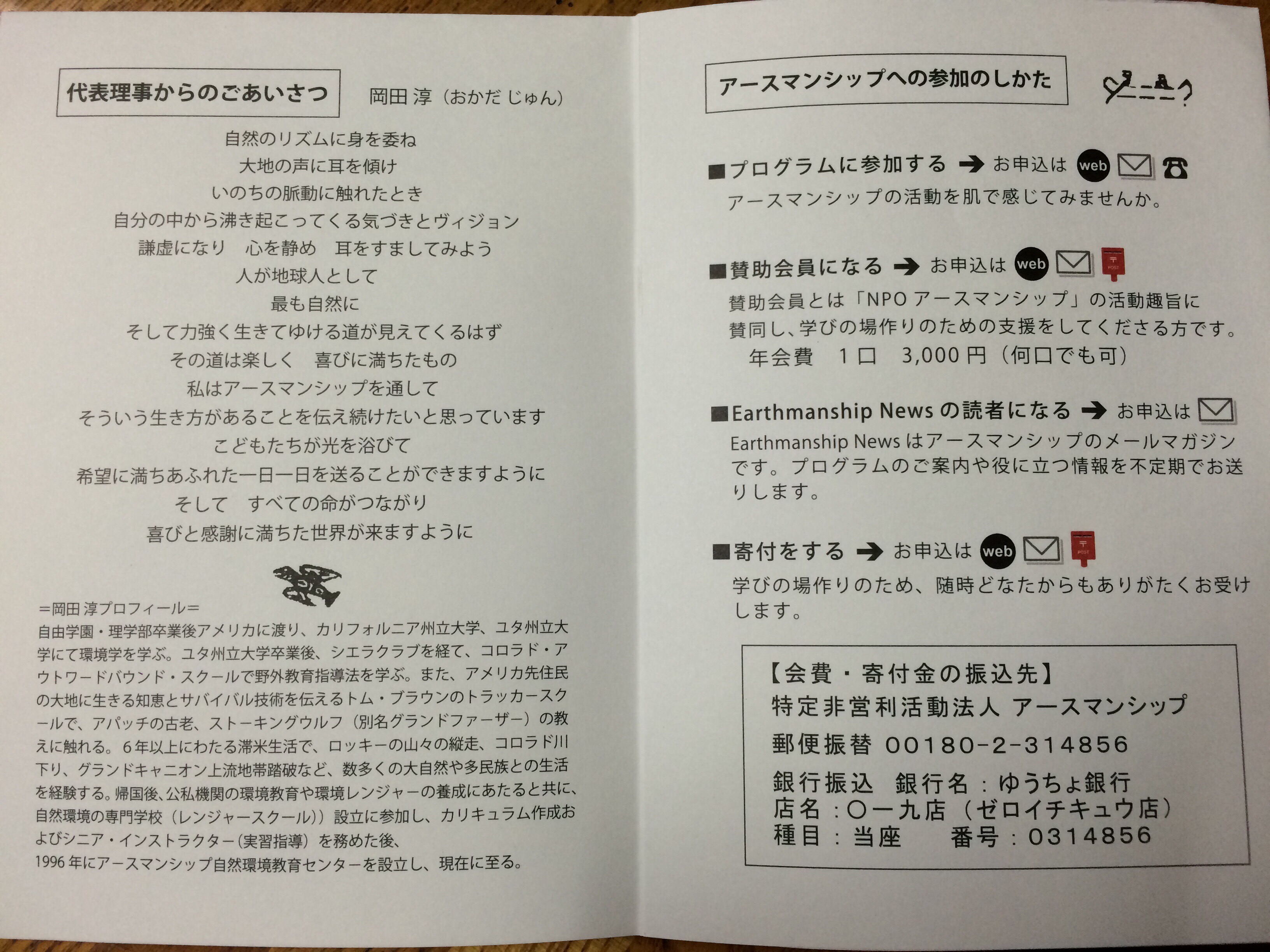2014
竹刀と真剣- 2014/10/26 -
ちょい向こうは晴れているのにダーッと大雨が降ってきた海を目の前にした不思議な朝。
本日朝一で千葉の富津にて、東善寺様の落慶式で奉納演奏させていただきました。
ベランダから釣りができるくらい海が目の前のホテルの一室をわざわざ控え室におさえていただいて、ピアノの竹井さんと朝から今日は帰りたくないね。と。笑
竹井さんに、お茶飲む?
と聞かれて、
お茶飲む!
と自分でもハッとするくらい真剣に大きな声で言ってしまい、2人でタガがはずれたように笑い転げました。
朝早すぎたかな?
本番前にさっくり晴れてみるみる眩しい日差し。
新しいお堂は木の匂いも清々しく、海からの爽やかな風と大雨の後の眩しい日差しが、祝福されているなーと感じました。
奉納演奏の後に海の幸をいただき、この辺ではカワハギが主流だそうで竹井さんと無言になって魚を食べました。
最近あさのあつこの時代小説をよく読んでます。けっこう剣士ものが多く、剣の道も音楽の弓と通じるものがあったりするなーと思います。
特に本番では、本番でしか感じないもの。本番でしか会得できないものがある。
竹刀と真剣が違うように、練習と本番は別物ですね。
あさのあつこさん。以前演奏で舞台が一緒だったのに、その時は読んでなくて、今だったら間違いなく会えて喜んだのにな〜。
聞いてみたいこと沢山あるなー。
2014
手紡ぎの先に見える大自然- 2014/10/24 -
たしか3歳の時に七五三で着物を着させられて大泣きして嫌がったので早々に脱がせられて以来私は着物を着たことがない。
この仕事をするようになり、衣装を考えるようになって、始めは成り行きでモンゴルの民族服を着ていたのだけれど、似合わない。
そんな時にはじめて感動する日本の着物に出会う。
それが宮崎県の綾町に綾の手紬染織工房を構える秋山眞和先生。
綾というと宮崎県の天然照葉樹林で有名な町。
以前その工房に演奏で呼ばれて行きました。
秋山先生の紡いで織る着物の展示会で沖縄の久米島にもコンサートで関わらせてもらい、着物を見るたびに龍の鱗だったり、蛍の乱舞だったり、綾の大自然を垣間見て感動していました。
秋山先生の着物は日本古来から伝わる小石丸という宮中で保護され飼育されている蚕を譲り受け、桑畑からご自分で管理され、蚕を飼育し、上質でも細い大変な糸を紡いで天然素材で染色し、手機で織る。
文にするとそうでもないが、実際は大変な事だ。
工房を隅々まで見せてもらい、桑畑にも行き、桑を大釜で茹でて染めたり、桑の実を収穫してジャムをつくったり、細かい細かい設計図を描いてそれを元に織る工程をみたり、藍染をさせてもらったり、いろんな経験をさせてもらいました。
で、その秋山先生が昨日伝統文化ポーラ賞の受賞式で上京されるということで、親しい方々とお祝いの会があり、そこへ出席して演奏もさせてもらいました。
なんかおかしいなー。
どうしても途中から丁寧な言葉遣いが似合わないような気になってしまいます。笑
いや。秋山先生はすごい人だし、作品は本当に感動するんだけど、あまりに気さくな沖縄のおじちゃんにしか思えないのであります。
気さくな人の所にはまた風変わりな気さくな人達が集まるな。というのが昨日のお祝い会の感想。
工房で作務衣を着ている姿しか印象にないので、受賞式の写真をみてやっぱり着物姿はかっこいいんだなー。奥様もかっこいい。秋山先生に織物の事を聞いても、こんなの誰でも出来ますよ。しか言わないけれど、奥様は本当に詳しくわかりやすく解説してくれます。
あーまた綾に行きたくなりました。
今度は山にもう少しゆっくり入りたいな。
秋山先生の作品を見ていると、先生の子供のような目が綾の大自然の何を捉えているのか、その目の奥に宿る先生の魂と綾の大自然の魂がどんな風に巡りあって、どんな風な反応をしたのだろうか、垣間見るような想像するような、そんな気になります。
馬頭琴は両脚を開いて挟むので着物は着れない。
その前にこれだけ手のかかった高価なものは買えない。というのもありますが。
でも素敵なショールや、藍染の手紡ぎの小物もあります。
日本橋MITSUKOSHIでもよく展示会していますので、興味ある方はぜひ。
2014
忘れるなよ- 2014/10/21 -
確か何気なくいいました。
まあ何気なくとは言っても楽器にとっては大きな問題である事には違いなく。
9月に棚田に取材されに行った時に夕方になるにつれ湿気が出てきて、はじめの取材で鳴っていた楽器がだんだん鳴らなくなってきたので、
湿気で楽器が鳴らなくなってますが、本番は日中なので今より音がずっといいはずです。
と取材の方に言ったのを、棚田の持ち主しげるさんは衝撃として受け止めていました。
一週間前の台風で棚田に雨が降り、3日前の世の中雨ではない日にその周辺だけ雨が降り、しげるさんは気が気じゃなく、毎年お客さん目線で、どうしたらお客さんが気持ちよく聞けるかに気を配って一年いろいろ思いながらたぶん棚田の大変!!な作業をこなしているんですけれども、
今年はじめてその美炎さんの湿気で楽器が鳴らなくなる、という言葉にこれは大変とそのことばかり心配して、それを廣田さんも察して棚田に降った雨の排水作業を連日してくれていました。
本当にありがたかったです。音は音楽の要ですからどうしようもありません。
こう書いていてまた思いました。
本当に棚田の持ち主しげるさんと、ヒロクラフト自慢のよその田んぼと公言している廣田さん夫婦は、次の一年間事あるごとに、来年を見据えて棚田に想いを馳せているのだと。
そしてそれに関わる方たちもまた、次の一年間を楽しみに、気ももみながら関わってくれているのだなーと。
だからこそ朝一番で棚田へと続く山道が参道におもえて、感謝が自然に湧いてくる。
慈しみながら関わる田んぼであるからこんなに特別な場所になり、一度来た人がハマるのだと思います。
共演者もまたハマるのです。笑
私もこの舞台になるべくいろんな人に体験したもらいたい気もするし、またこの人とやりたい気もするし、舞台の大きさも限られているので年々増えるわけにもいかず。
でもどちらにせよ、一期一会、今だけの音、今だけの風、今だけの人の集まり。
それであることには間違いありません。
朝一しっとりと濡れていた石舞台。設定をしてお客様を待つ間にみるみるモヤがたちあがり、お日様の力はなんて偉大だろうと思いました。
こんな風に演奏が始まるまでにいろんな事柄に感謝して感動できる舞台に出会えた事が
私がこの棚田コンサートをご褒美みたいだと思う所以でもあります。
演奏後の懇親会で振る舞われる地域のお母さん達の朝から大釜で炊き上げる棚田米と山の恵みのご馳走ももちろんご褒美です。
私何かいいことしたっけ?と思わず振り返り、いや。してないな。これはいいことしたご褒美じゃなくて、この感謝と里人と自然が一体となって作用する事でうまれる音を、忘れるなよ。という事なんですね。
2014
里守人おじさんず- 2014/10/20 -
朝いちばん
棚田の石舞台目指して山に入る。
主催のヒロクラフトさんの家の脇に山の棚田へ続いている道の入り口がある。
そこから参道がはじまっている。
朝いちばんに来ているのに、すでにきれいに掃き清められているのだ。
これはこの梅平地区のヒロクラフトさんが言うところの梅平里守人のおじさんず。
4回目になる今年、毎年顔をあわせる棚田の持ち主しげるさんの同じラインにいる気がするおじさんずが3人いらっしゃるのだが、しげるさん含めこの方達がなんだかすごい。
こんな風に山の棚田にお客様を招くというのは初体験である、その第一回目から、お客様が気持ちいいように。
危なくないように。
楽しく聴けるように。
その一心で、人の田んぼの参道を数日前から、たぶんもっと前から。
草刈り、薮払い、当日朝は神社の参道ばりに掃き清められているのだ。
そして第一回目から、コンサート後に私にそれぞれのおじさんずが、終わった後に、これだけのお客さんが来たんだからゴミの一つも落ちているだろうと、目を皿のようにして意地悪いくらい探したけど、どんな小さなゴミも落ちていなかったんだよ!
と嬉しそうに教えてくれたり、
お客さんがね、気持ちよく棚田にきて、気持ちよく聞いて帰ってくれるのが何より嬉しいんだよ。
とか
みんな帰り道、ほんとうに今日は来てよかったねーと誰もが言っていたよ。誰一人文句らしいことをいってなかったよ。と嬉しそうに報告してくださる。
私にはこのおじさんずが天使のように感じるのですが。笑
守護天使かな。梅平里守人だから。
この山の棚田は不思議なくらい音が伸びて美しく響く。
馬頭琴は完全に生音だが、私は自分の音が山の上でどんな風に聞こえるか聞いた事はないけれど、弾いていてホールのように音が返ってくるとかでもなく、普通の野外のように散って消える感覚でもなく、本当に伸びていくのが感覚としてわかって面白い。
その音に対してどうやら自然が反応してくれる。
毎年お客さんが、この曲のときにトンビが舞っていたとか、この曲で赤トンボがいっせいに出てきた、とかこの曲で風が後ろの森を順番に吹き渡っていたとか。いろいろ教えてくださる。
この場所は音が不思議に作用する。そこにはどうもはじめっからこのおじさんず以下沢山のおじさんずに繋がる人達のあたたかい気持ちが作用している。
私は毎回日の出の朝いちばんにこの参道を通って棚田の石舞台にお参りする。
静かに棚田の中で今日どのように音を巡らせるかイメージする。
それができるのもこの参道のおかげなのです。
2014
山形の夜は川の底- 2014/10/15 -
山形の夜
結果、原住民カッパ会議。笑
アースマンシップを主催する岡田さん夫婦とそのお仲間と、山の中のそもそも人が手を加えたために滞ってしまった場所を整備して、空気の流れを作る事で水の流れを復活させ、その流れの浄化作用を利用して、溜まっていたものを流し、最終的には光のさす爽やかな場所に再生する様を見せてもらい、すごいな〜と思いました。
管理するのではなく、お手伝いする。
山形の家は私が高校時代三年間寮生活をした学校のすぐ近くにあり、そこにアースマンシップの方達と泊まり、その家の隣の家族と、高校時代の村の先輩とが集まり、子供の頃何したかって、川に潜ってたよなーっていうカッパ話しをひたすら。
滝に巻き込まれた経験や、大物を見つけた瞬間の気持ち。
深い所で息をひそめていると、このまま息をしなくてもいつまでも大丈夫と思えてしまう感覚。
カジカや岩魚の話し。
デカイ鯉がいたこと。でも鱗がかたくて突きがささらなかったこと。
大物の鯉は目をゆっくりふさいで、横から抱き寄せてとるということ。
聞きながら、水ぞこの不思議な青い世界に。
そしてアースマンシップの岡田さんの話はほぼ人生の流れを語ってもくださったので、ここで簡単に紹介するのが難しいのだけれど、あらゆるサバイバル術、ネイティヴアメリカンの知恵、グランドファザーを書いた著者との出会い、山や川でもしこんな事があったら、感覚を開くということ。
というその場の誰もが身を乗り出して聞き入ってしまう不思議な時間でした。
この地域に暮らすおじいちゃんおばあちゃんの知恵がどんどん失われていく実感と、川での遊び方を子供達に伝えられていない事とか、この原住民カッパ会議でもって、次回、なんか手がないものか・・・笑
アースマンシップさんの紹介文がありましたので、興味ある方は写真の文章を読んでみてください。
あるいはホームページ
www.earthmanship.com/
もしくはフェイスブックページでアースマンシップで探してみてください。